電化製品を複数使いたいときや、コンセントの場所が遠いときなど、日常的に延長コードを使っている方は多いでしょう。しかし、その便利さの裏には、意外と知られていない大きなリスクが潜んでいます。ここでは、延長コードの危険性について詳しく解説し、安全に使用するためのポイントを紹介します。
延長コードが抱える主な危険性
1. 発熱・火災のリスク
延長コードは多くの電気機器を接続できる反面、定格容量を超えるとコードが発熱し、最悪の場合は火災に発展することもあります。特に、以下のような使い方には注意が必要です。
- 定格容量を超えて電化製品を接続する
- 延長コードを束ねたまま使用する(熱がこもる)
- 家具の下敷きにして圧迫する
2. 絶縁被膜の劣化による感電事故
長期間の使用や無理な曲げ・踏みつけなどで、コードの被膜が傷んでしまうことがあります。これにより内部の電線が露出し、感電事故を引き起こすリスクが高まります。
3. トリップ(つまずき)事故
床を這う延長コードにつまずいて転倒する事故も報告されています。特に高齢者や子どもがいる家庭では、コードの配置に注意が必要です。
4. タコ足配線の落とし穴
コンセント一つから何本もコードを引き出している、いわゆる「タコ足配線」は、見た目以上にリスクが高い行為です。電流が集中し、ブレーカーが落ちたり火災が発生したりする恐れがあります。
特に注意したい場所とシチュエーション
● キッチンや洗面所など水回り
水気の多い場所で延長コードを使うと、漏電や感電の危険があります。防水仕様の製品を選ぶか、極力コードの使用は避けるようにしましょう。
● ホームオフィスやパソコン周辺
パソコンやプリンターなど電力を多く使う機器を複数接続すると、知らないうちに定格をオーバーしてしまうことがあります。個別スイッチ付きの延長コードや、電力量を表示するタイプのタップを活用すると安心です。
● 冬場の暖房器具
電気ストーブやこたつなどは消費電力が非常に高く、延長コードを介しての使用は避けるべきです。どうしても使う場合は、必ず使用機器の消費電力と延長コードの定格容量を確認しましょう。
安全に使うためのポイント
- 定格容量を必ず確認する:延長コードには必ず”○A”や”○W”などの定格が記載されています。接続する機器の合計電力がこれを超えないように注意しましょう。
- コードは束ねずに使う:使わない長さのコードはまとめてしまいがちですが、熱がこもって危険です。可能な限りコードは広げて使用しましょう。
- 使用前に目視チェックを:コードが裂けていたり、プラグ部分が焦げていたりした場合は、即座に使用を中止してください。
- 古くなったら買い替えを:延長コードにも寿命があります。長年使っているものは、内部劣化により発火リスクが高まるため、定期的な買い替えをおすすめします。
- 雷サージ対応モデルの選択を:落雷による家電製品の故障を防ぐには、雷ガード付きの延長コードが有効です。
延長コードと正しく付き合う
延長コードは非常に便利な道具ですが、間違った使い方をすれば重大な事故につながりかねません。火災や感電などのリスクをしっかりと理解し、正しく使用することが大切です。
ご家庭や職場で延長コードを使っている方は、ぜひ一度、今の使い方を見直してみてください。安全で快適な電気ライフを送るために、今日からできる小さな注意が大きな安心につながります。


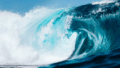
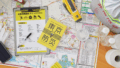
コメント