近年、「地震が少なくなったように感じる」という声を耳にすることがあります。確かに、ニュースで大きな地震の報道を目にする機会が減っているようにも思えます。しかし、本当に地震の発生数が減っているのでしょうか?それとも私たちの「体感」や「報道の傾向」による印象なのでしょうか?
この記事では、最近の地震活動の傾向、過去との比較、地震が少ない時期に潜むリスク、そして今後に備えるための対策について、分かりやすく解説していきます。
実際に地震は減っているのか?
気象庁の観測データによれば、2020年代に入ってから、日本国内で観測される震度1以上の地震の数は、年間で1000回前後と、過去10年平均と大きく変わっていません。一方で、震度5弱以上の大きな地震は、確かにここ2〜3年でやや減少傾向にあるように見受けられます。
たとえば、2011年の東日本大震災の前後には、余震を含めて大規模地震が多発していましたが、現在はそうした連続発生の時期と比べると「静穏期」にあると言えるかもしれません。
ただし、「静かであること」が「安全である」ことを意味するわけではありません。むしろプレートのひずみが蓄積している証とも考えられ、次の大地震の前兆である可能性も否定できません。
地震が少ないと感じる理由とは?
私たちが「最近地震が少ない」と感じる背景には、いくつかの要因があります。
- 報道頻度の変化:地震そのものの発生数が変わっていなくても、ニュースで取り上げられる地震が減れば、体感として「減った」と思いがちです。
- 大規模地震の不在:震度5弱以上の目立つ地震が少なければ、印象として「最近は静かだな」と感じるのは自然です。
- 災害報道の分散:コロナ禍や異常気象、国際問題など、他の重大ニュースが多く報道されると、地震の扱いが相対的に小さくなります。
- 地域差の影響:地震が頻発している地域とそうでない地域があるため、自分の住んでいる場所が静かであれば、全国的にも静かだと錯覚する傾向があります。
静かな時期こそ要注意──プレート境界型地震の前兆か
日本は4つのプレート(ユーラシア、北米、フィリピン海、太平洋)の境界に位置する、世界でも有数の地震多発国です。特に、南海トラフ地震や首都直下地震といった大規模地震は、過去にも静かな時期の後に突如として発生しています。
たとえば、1944年の東南海地震、1946年の南海地震は、それ以前の数年間で大きな地震活動が少なかった「静穏期」を経て起こったものです。また、東日本大震災の前にも、2008年以降の東北地方は比較的地震が少なかったという指摘もあります。
つまり、「最近地震が少ない」ことは、「エネルギーが溜まっている状態」である可能性があり、次の大地震が近づいている兆候である可能性も考えられるのです。
地震の予知は可能か?
残念ながら、現在の科学技術では「いつ・どこで・どの規模の地震が起こるか」を正確に予知することはできません。しかし、ある程度の確率予測や、過去のデータを元にした長期評価は行われています。
たとえば、南海トラフ巨大地震については、今後30年以内に70%〜80%の確率で発生するとされており、国や自治体もさまざまな対策を講じています。また、首都直下地震についても、今後30年以内に70%の確率で発生するとの予測があります。
このように、予知はできなくとも「予測」は可能であり、それに基づいた備えは今からでも始めることができます。
今できる備えとは?
地震のリスクに対して備えるためには、次のような行動が重要です。
- 防災グッズの準備:水・食料・懐中電灯・モバイルバッテリー・簡易トイレなどを最低3日分備えておく。
- 家具の固定:家具の転倒防止器具を使って、倒れやすい棚やテレビなどを固定する。
- 家族との連絡方法の確認:災害時に使える連絡手段や避難場所を家族で話し合っておく。
- 防災アプリの活用:緊急地震速報や災害情報を即時に受け取れるアプリをスマートフォンにインストールしておく。
- ハザードマップの確認:自宅や職場がどのような地震・津波のリスクに晒されているかを把握しておく。
まとめ:油断せず、今できる準備を
「最近地震が少ない」と感じることは、ある意味で「平和な証」かもしれません。しかし、静かな時期こそが大地震の前兆であるという指摘も多く、決して油断してはいけません。
日本に住む以上、地震のリスクは避けられないものです。だからこそ、科学的な知見と経験則に基づいて、冷静に、そして確実に備えておくことが、私たち自身と大切な人の命を守ることにつながります。
地震が少ない今こそ、防災のチャンスと捉えましょう。

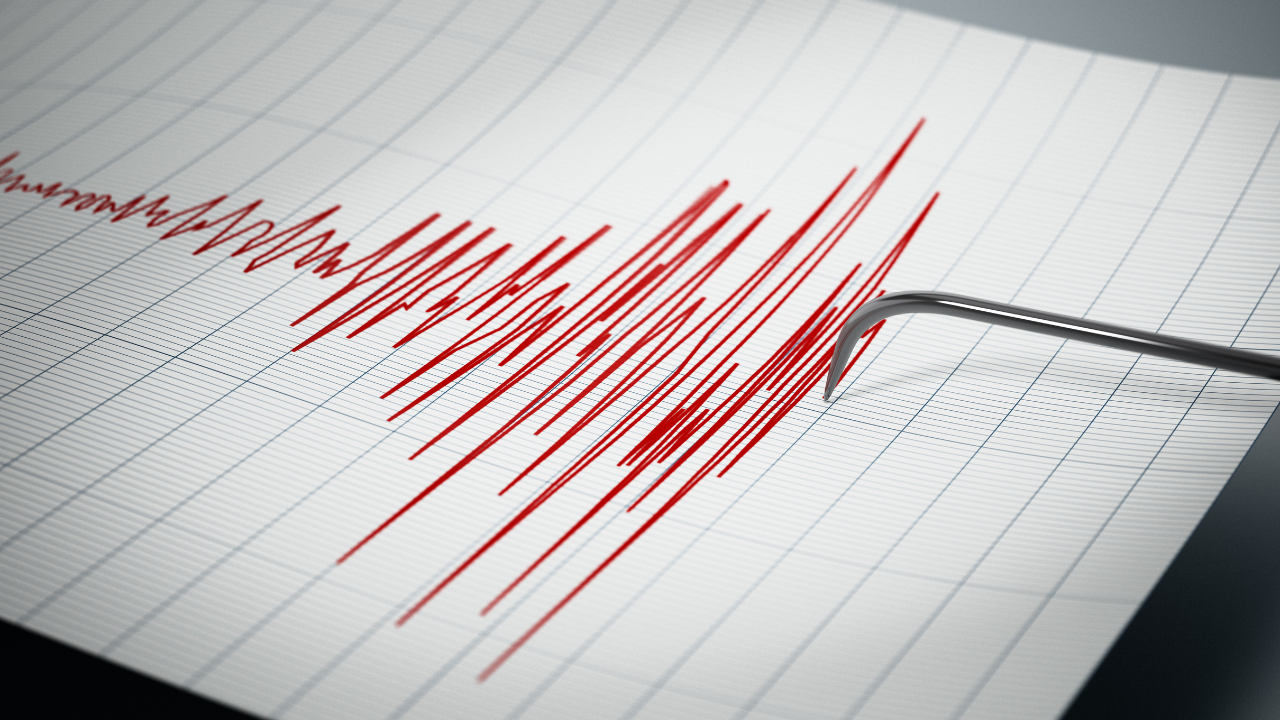


コメント